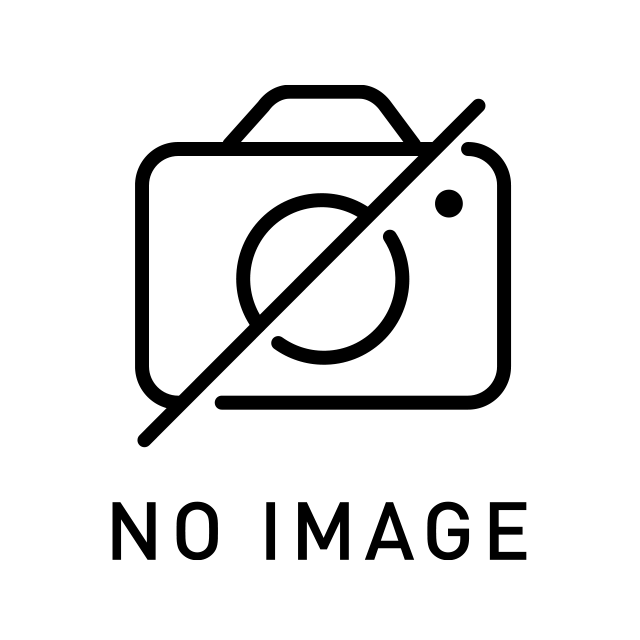初披露
私が持っているフラウト・トラヴェルソ。(双方とも A≒415Hz)

Stanesby junior
このうち、下の白いものはプラスチック(ABS 樹脂)製で、アウロス社の樹脂製ステインズビージュニアAF-3である。プラスチック製とはいいながら、結構な重さがある。ステインズビーの象牙製のオリジナルをコピーしたもので、その重さに近付けたからである。
ステインズビーはトラヴェルソの中でも傑出している名器で、ヘンデルに近しかった奏者が愛用していた。本物は弦楽器にも負けないほどの馬力をもち、ストレートで明るい音色が特徴である。この写真にあるプラスチック製コピーのほうは、音量は落ちるものの、音色は本物とほぼ同じである。素人であれば耳で区別がつかないかも知れない(下手な奏者は問題外であるが)。
ちなみに、本物は象牙であれば数百万円、木製であったとしても数十万円はする。それとほぼ同様の音色をもつコピーが、4万円ほどで手に入るというのは幸せなことだ。
Grenser
上の如何にも木製といったほうは、柘植製の A.Grenser モデルで、Alain Weemaels 氏によるコピーである。バロック後期から古典が得意なモデルだが、私が所有するこの楽器は、不思議というより奇跡的な楽器である。
バロック期の例えば Jacob Denner モデルであれば、低音が豊かで高音は鳴りにくいが、古典期のモデルは、高音が鳴りやすい代わりに低音が鳴りにくいのが一般的である。ところが、私のこのグレンザーは、低音も高音も鳴る楽器なのだ。つまり、バロック期と古典期の楽器のよい部分を足し合わせた、謂わば尺八と篠笛を継ぎ合わせたようなものだ。
傷
そうは言いながら、この楽器がもっている能力をフルに引き出そうとして鳴らそうとすると、音域毎のバランスが崩れ易く、また、音程が不安定になる。じゃじゃ馬なのだ。
本当に機嫌が悪いときは鳴ってくれないし、鳴ったとしても音程がとりにくくなる。ところが、機嫌がいいと、こちらのコントロールしたい通りに鳴ってくれる。私はじゃじゃ馬を飼い馴らすのが好きなほうなので、こいつが可愛くてしょうがない。ところが、普段は、殆ど、こいつに相手してやっていない。それは、傷を付けてしまうからである。
ちょっと拡大してみる。

この画像の一番左のホールの右下に注目すると、上下とも「傷」が付いている。爪の引っ掻き傷だ。グレンザー(木製)の方を更に拡大してみると、こうなっている。

可哀想なことになっている。これは、決して、爪を伸ばしているからこうなったのではない。爪の処置は殆ど毎日している。しかし、それでも、ちょっとした条件で、爪が当たってしまうのだ。
それは私の指の障害が原因している。これを見てほしい。

両方の人差し指の関節を合わせたときの画像なのだが、左の方が若干短い。小学生のときに、先端を5ミリほど切断した。
このため、この指の爪を肉を切らないギリギリのところまで切ったとしても、このホールを急激に塞ごうとすると、どうしても当たってしまうのだ。
調整技術
フルートは一般にそうなのだが、左手人差し指の付け根、下唇、右手親指の3点で、基本的には支えている。そした、その支えになっている「左手人差し指」の先端でホールを塞がなければならない。管の口径というのは、当然、「付け根」から「先端」までの長さの一般的な規格も考慮されて今ある形になっているわけだから、規格外の指には合わないようになっている。当たり前の話だ。
トラヴェルソの場合、ホールと指との間が僅かでも空くと、音程が変わってしまう。完全に塞がねばならない。一方、管の「角度」が上下左右に少しでも変わると、「音のポイント」がズレてしまい、音程が変わるか、音が出なくなってしまう。
従って、寸法にしてミリ単位、角度にして1度単位の微調整をしながら、演奏している。それぞれの音の「鳴り」の丁度いい身体的状態というのがあって、これを逃すと、全体のバランスが崩れ、「音階」すらきちんと吹けなくなる。楽器を支える点もホールを押さえる点も、遊びを許さないほどに、その位置が決まっているのだ。
私がもっているような左手人差し指の障害は、致命的だと言ってよい。だから、この致命的な欠陥を調整技術の訓練によって克服する以外にないのである。
等価交換
私が今現在所有する2本のトラヴェルソのうち、ステインズビー(樹脂製)は「ポイント」が狭い。「ポイント」というのは、「歌口」に息を当てたときに音が鳴る部分である。
トラヴェルソは、現在のモダン・フルートと異なり、おそらく「串」ぐらいの細さの「気流」を送り込んでやらなければ、音は鳴らない。その「気流」の口径を、一般のトラヴェルソにおけるよりも、更に、細くしてやらなければ、ステインズビーは鳴ってくれないのである。だから、初心者の中には、この樹脂製のステインズビーの「鳴りにくさ」の原因はその「材質」にあると思っている人があるが、そうではなく、「正確な息のコントロール」をしていないことにある。
見方を変えれば、このステインズビーを完全にコントロールして鳴らしきるように訓練しさえすれば、どのトラヴェルソもコントロールできるようになるということになる。
それで、私の場合には、どんな難曲であったとしても、譜読みの段階では、このステインズビーを使用することにしている。それのみが、自分の障害を克服する道であるのだ。
実は、私は、この楽器を奏する上での更なるハンディをもっている。先ず、歯並びが悪いために、普通の奏者に比べて、上記の「気流」を整える精度を上げなければならない。また、多汗症であるために、特に、樹脂でできた楽器のほうは滑り易く、更には、ホールが塞がらない場合があり、やはり「フィンガリング」の精度を上げなければならない。
このため尋常ではない研ぎ澄まされた感覚が必要とされる。それは理屈を越えている。 障害を克服しようとして齎されるもの — それは、痛みである。
左人差し指先端の切断面は、通常でも、他の指と感覚が異なる。度重なるホールの開閉によって神経が過敏になり、最終的には疼(うず)く。楽器のバランスの崩れを修正するために過度に力が入れば、左人差し指の付け根は圧迫を受け、そのままの状態で頻繁に行われる同指によるトリルは、痺(しび)れを齎す。
理想の響きを得るためには、苦痛という代償を支払わねばならない。これが「美」と「苦」の等価交換の法則である。
ダメージ
グレンザーは、ほぼ仕上がりができた曲か、難曲で、その楽器のもつバランスを試すことが必要な場合にのみ、現在では鳴らすことにしている。久しぶりに触るときには、恋人と再会するような感覚になることがある。
だが、私のところに来たばかりに、こいつは傷付いている。爪の引っ掻き傷の他にも、ベルギーから遠い異国の地である日本に送られてきたばかりに、その材質が柔らかいこともあり、歪んでいる。下は「頭部管」のジョイント部の画像である。

この画像では余りはっきりとはわからないかも知れないが、「頭部管」は「真円」にはなっておらず、ほんの僅かながら「上下」に長くなっている。気候における湿度の違いが、楽器にダメージを与えているのである。
このため、この画像でいえば、右の内側に細い「ヒビ」が入ってしまった。つまり、「中部管」は「左右」で押さえられていることになる。「上下」にあるわずかの隙間のために、管が固定されず、演奏の間に抜けてくる。ということは、管内の圧力の状態も不安定になり、最終的に管の鳴り響き全体に影響を及ぼす。
これを修正するために、ジョイント部に「紙」を噛ませてやる。これによって管が無理のない力で固定される。
この気候からくるダメージの他に、私の「汗」が、こいつを傷付けている。Weemaels にメンテナンス (voicing) をお願いして戻ってきたときに、私の汗は、一般の人のそれよりも酸性が強いと指摘された。だから、頻繁にオイルを塗ることが必要になる。
存在の痛み
この楽器は生きている、そして、いつかは朽ちる — 存在の儚さを象徴する。だからこそ愛おしい。
こいつは、私と痛みを分かち合った相棒だ。私が生きている限り、こいつは傷付いていく。こいつがダメになるのが先か、私が死ぬのが先かわからない。でも、こいつは誰にも渡さない。私と一緒に棺桶に入る。こいつを私から引き離す人間を、私は永遠に呪うだろう。
それまでの間、気の済むまで歌わせてやろう。
旧ウェブ日記2010年3月8日付