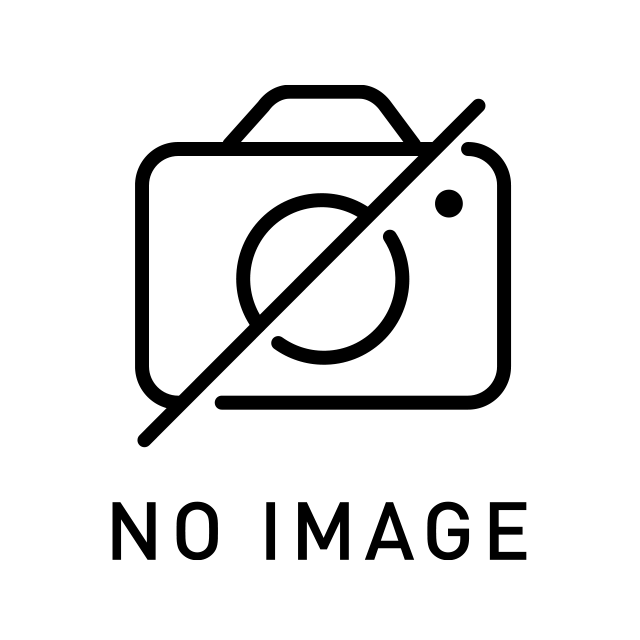話は前後するが
7月20日(木),期末試験監督のために横浜校舎に出校し,試験監督の合間をみてメールの確認をしていたところ,長らく連絡のなかった旧友からメールがあった。ごくごく短い内容であったが,送信されてきた件名に共通の学友の名が書かれていたことから,一瞬にして只ならぬ事柄の連絡であることは察しえた。その学友の弔報であった。
その後,メールはその語られる内容の重きを様々に変えながら交され,錯綜と困惑と不安と悲嘆とが入り乱れながら,この日が迎えられた。幾つかの条件が整わねば決して実現されることはなかったに違いないが,奇しくもそれが揃うこととなった弔問の日ではあった。
正直に言えば,私は,ここに書くことも書かないことも躊躇われる。全てを書くわけにはいかないが,全く書かないわけにもいかない。全てを忘却の淵に追いやりたいが,全ての記憶を消し去ることもできない。だから多少とも曖昧な仕方で書き残しておくより他ないのだ。
弔問
我々が焼香に訪れたのは,彼が新たに住み始めたマンションだった。弔問客は,我々夫婦の他,彼の大学の後輩が一人,彼とおそらくは一番仲のよかった大学の同僚夫妻 — この同僚が上記の最初の弔報をメールしてくれた — ,そしてその他の大学の同僚名であり,後から遅れてもう一名が来た。
奥さんが出迎えてくれたのだが,実は,我々は誰も彼が結婚していたということすら知らなかった。そこへきて,彼の奥さんを名乗る人物から,上記の同僚に連絡があり,そして,そこから私に連絡があったため,最初は何が何だか理解できなかった。後に,この奥さんを名乗る人物から,故人のアドレス帳に記載されたメールアドレス全部に,連絡が送信されてきたために,私にもその内容が届くことになった。
彼は,昨年,正式にある大学の専任教員になり,また,結婚もした。数年間,非常勤講師を複数の大学で兼任していたから,研究拠点が一つに定まり,収入も安定し,身も落ち着いて,いよいよこれからというときであったはずだ。
奥さんとのお付合いが始まったのは,一昨年前からだという。普通に考えるならば,最も幸せで希望に満ち溢れているはずの時期ではないか。そうでありながら,彼は,残りの生を共にしようと誓い合ったはずの彼女を残して,独り逝ってしまった。
弔問に訪れた彼をよく知るはずの学友達全ては,彼が逸った理由が今でもわからない。一番仲のよかった同僚がたまにやりとりしたメールや奥さんが証言する生前の彼の様子を総合してみて,我々には,ごくごくありきたりの筋道しか想像することしかできない。
証言
奥さんの証言によるならば,付合い始めて間もなく結婚し,その直後から鬱気味だったという。やっと手にいれた職場を相当にいやがっていたらしい。昨年の夏も,自殺をほのめかすことを言って失踪し,奥さんが必死に捜索したとのことである。
職場に対して彼が余程悩んでいたということは,彼を引き抜いた方も,彼から直接の相談を受けていたということから察しえよう。しかし,非常勤を得ることすら大変なこのご時世に,専任になることができたのだから,普通はもったいないことだと思うだろう。彼もそのことは承知していた。
だが,「研究活動」と「教育活動」(そして「事務仕事」)との間にある歪みについても,彼は誰よりも理解していた。彼が,自らの研究について,ある使命感をもっていたことは,その指導教官であったSF先生も証言するところである。こうした,「教育活動」と「研究活動」との間にある歪み,もっと言えば,「教育活動」における不毛な体制によって「研究活動」が蔑ろにされ妨害されるという事実は,私もこの日記に幾度となく書き記してきたことであり,まさにそのこと故に,今このときにも,私は「研究活動」を辞めているのである。
彼の学問に対する純粋で直向きな志は,今現在自らが置かれている状況を許さなかったではあろう。そればかりではなく,具体的なことはわからないにせよ,教育組織の中で,他の誰に理解できない屈辱的な事柄を彼が抱えていたということ自体は,容易に推察されうる。今直ぐにでも,そのような状況を脱したかったのだろう。
公募
そのためか,彼が就任する前年にあった母校での公募人事に,いわば最後の希望を託していた節がある。というのも,これも幾つかの証言を寄せ集めてわかったことであるのだが,彼に対して,以前から直接的な打診があったのだということである。
実は,この公募に関しては,私の方にも呼び掛けがあった。私の場合には,大学院時代の指導教官からその勧めがあった。しかし,その余りに漠然とした内容と,指導教官のかねてからの無責任な態度とに辟易していたので,ついに書類提出後まもなくして辞退申し出のための書類を作成した。
それのみならず,その文書の中で,指導教官から受けたこれまでの数々の処遇はアカデミック・ハラスメントにあたり,それぞれに異なった所属研究機関に所属している今,これ以上の執拗な行為に対しては法廷措置も辞さない構えであること,また,その様な事態が生じないことためにも,今後は,この指導教官から当方に連絡をとる必要がある場合には,必ず信頼できる第三者を介して頂きたい旨を伝えた。また,この私がそれまでに入会した学会のうち,この教官が深く関わっているものを退会した。
私が辞退したあと一つの理由は,公募の内容に鑑み,私が辞退すれば,その条件に見合う同僚達がそのポストに就くことができる可能性が高まるからである。
私の場合には,現職の待遇に対しては全く満足しているわけではないが,しかし,逆に,研究に関しては,現職に就くまでも決して満足できるものではなかった — 拙書の「後記」においても記した通りである — わけであるから,かりに昔の柵のある古巣へ戻っていったところ,この先,研究上の障害が全てなくなるということが保証されるわけでもないと思っていたから,このままでも構わないという諦めをもっていた。だから一層相応しい人物をと思ったとき,先ず,彼が念頭にあったのである。
ところが,そもそも当該公募人事について,彼は — そして,少なくとも私が予想していた彼を含めた幾人かの学友らは — 全くの埒外であったということなのである。この現実を彼は全く予想もしておらず,また,そもそも信じ難いことであったのだろう。
ともかく,彼にとっての唯一の希望の光は潰えたのである。
最後の仕事
しかし,それでも,彼はそんなに簡単に折れる様な人ではなかった。一度決断したら,それを徹して行う人間であった。現に,彼が意を決したのは7月16日(日)から17日(月)にかけてであろうということであるが,13日(木)には,遺作となった共訳書の最後のチェックを済ませ出版社に連絡をとっているし,14日(金)の教授会にも出席している。彼なりに責任は果たしたつもりだったのだろう。
確かに,彼は鬱にあったかもしれない。奥さんはそのことで心療内科に相談に行ったらしいが,本人が来ないことにはどうしようもないと言われ,彼を説得しようとしたが,頑強に「心理学というのは嘘だ」と拒んでいたという。自覚がなかったのだと言われればそれまでのことであるが,社会に対して弱気になっていたわけでもないだろう。従って,鬱であったことが直接的引金でもない。
また,彼が最後まで完全に決断しきれていたのかといえば,そうともいえない。というのも,彼は昨年夏に未遂を起こしたときもサービスエリアで駐車していたらしいが,今回発見されたときも同様だった。そればかりか,直接の死因は七輪による一酸化炭素中毒であったが,これは第一発見者であった警官の証言らしいが,不思議なことに,車の窓はガムテープで隙間を塞いでいたにも拘らず,ドアにロックがかけられていなかったというのだ。
「不思議なことに」というのは,普通は,失敗を恐れて必ずドアにロックがかけられているものであるということなのだが,彼の場合には,ロックされていなかったというのだ。即ち,発見され,未遂に終わることをも期待してすらいるように思われるのだ。
以上のような幾つかの証言が集まり,おそらく八方塞がりになっているところに突発的な鬱症状が重なり,自分の生死を運命の手に預けた — いわば「ロシアン・ルーレット」のように,死ぬときには死ぬし,生きるときには生きる — のだろう。実際には,余りに遅くに気付かれたというだけのことなのだ。
推測
ここからは私の独断的な推測なのだが,彼は奥さんとの付合いが始まってから,自分自身の内面的な弱みを見せるようになったようだ。このため,彼のことを昔から知っている我々のもっている彼への評価と,奥さんがもつそれとが,余りに食い違うので,我々はそれに驚いていた。我々には決して見せなかった表情を奥さんはずっと見守り続けてきたのだ。だとすれば,これまでの彼の彼自身に対する厳しさ — 研究生活における,そして,人生そのものにおける — が緩み始め,更に,彼自身は,それを恐れていたのではないだろうか。
私は,彼にとって「結婚」そのものが悪かったのだと言っているのではない。そうではなく,誰にとっても「結婚」というのは,それまでの古い自分の枠を積極的に壊し広げていく体験に他ならない。彼は彼女に巡り合えて幸せだったと思う。しかし,それまで培われてきた彼の人生からすると幸せに過ぎたのだ。
彼は,おそらく旧友の誰もが想像できないくらいに,自らに厳しかった。そう生きることが彼にとっての人生だった。その態度が崩れていくことに我慢できなかったであろう。ある証言では,「僕はダメになっていく」と言っていたらしい。
もう一度言うが,彼にとって,彼女は最も理想的な女性だった。実際お会いしてみて,非常に常識的で,社交的で,それでいて可愛らしい方だ。そして,このような絶望的な悲しみにあるべきときにも,気丈に振る舞っていた。付合い始めて間もなく,彼の面倒をみ続けなければならなかったのだ。気の毒なのは独り残された彼女だろう。だが,彼は,それを知ってはいたに違いないが,それでもそうせざるをえなかった。
新たな職をえ,新たな土地に住み,新たな生活を営むという幾つかの条件が重なれば,大変になることは,誰しもが経験する。そして,誰しもがそれに耐え,決して自らの命を絶つなどという愚行には至らない — 鬱である要素をこれに加えたにせよ。
しかし,心のバランスというのは,その人間にしかわからない。私が思うに,彼は,「結婚」というこの人生の節目を通じて,自らのうちにある「厳しさ」と「甘え」との間にあるバランスを崩したのだろう。私が指摘したのは,バランスをとるべき二項の名辞に過ぎない。それを自らどのように昇華するのかは,その人の努力にかかっている。実際には,彼にとって初めて自分を完全に受け入れてくれる存在が現れた,ただそれだけのことだ。
推測は推測に過ぎない。だが,現代日本社会において,純粋に学術的なことをやり遂げるためには,余りに当然に人間的なことを犠牲にせねばならない。彼のように純粋な人間は,それに耐えることができなかっただけなのだ。
彼の犯したことは確かに愚かだ。しかし,彼を責める人間を,私は決して許さないだろう。
旧ウェブ日記2006年8月12日付