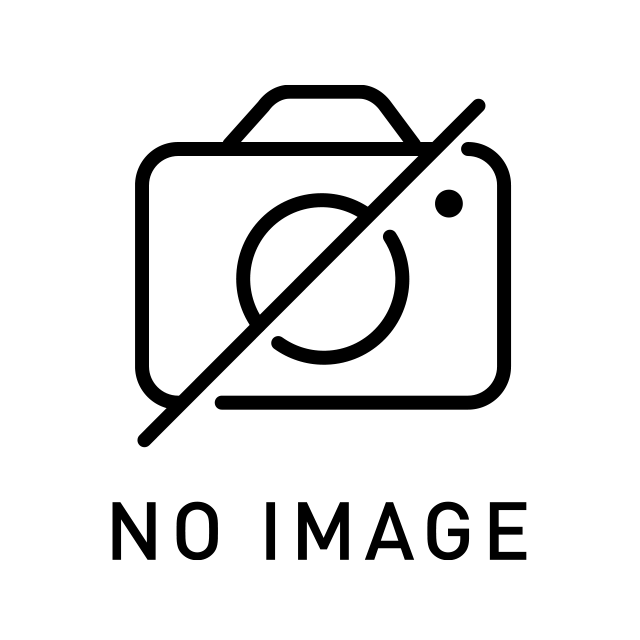声の如くに
西洋音楽の伝統は,「器楽」を排除するところから始まった。そして,ボエティウス (Anicius Manlius Severinus Boethius, c.480-524AD)による「音楽の3区分」 — 宇宙の音楽,人間の音楽,機関の音楽 — は,この考えに対する中世の理論的基礎を与えた。「器楽」は「声楽」に劣るのである。しかし,その「声楽」すらも「神的比例秩序」の模倣に過ぎなかった。
近代音楽は,先ず,「声楽」の改革から始まった。「人間の魂」に固有の運動,即ち,感情(情念)の表現を技巧化していった。器楽伴奏付き歌曲の形態であるモノディアがその典型である。しかし,そのときにも「純器楽」は「声楽」の模倣に過ぎなかった。
「純器楽」そのものが「人間の魂」に固有の運動を表現する技巧を手にするためには,その独自の発展がなければならなかった。「楽器」の改良は,「人間の声」の如くなることをひたすら目指して為された。
ヴィオール
フランスのヴィオール(ヴィオラ・ダ・ガンバ)の盛衰は,この人間精神の盛衰と並行する。ヴィオールの歴史はマレ (Marin Marais, 1656-1728) なくして語ることはできない。マレはこの楽器の名手であり,ルイ14世の宮中で栄光を手にした。
このマレの出版した《ヴィオール曲集第2集》に〈人間の声 Les Voix Humaines〉という曲がある。
「ニ長調」でありながら,例えば,バッハがその調性で象徴するような「天上の光」は,そこにはない。それは木漏れ日のような優しさをもつ。
次は,サヴァール (Jordi Savall) の独奏によるものである。
巡り逢う朝
しかし,何故に,それは「人間の声」なのか。
1993年に日本で公開されたフランス映画『めぐり逢う朝 Tous les matins du monde』は,このマレに影響を及ぼしたと言われる師サント・コロンブ (Sainte-Colombe) の音楽に光を当てた。
史実ではない。何故ならば,宮中で名が知られていたヴィオール奏者でありながら,幾つかの楽譜が出版された以外,記録が殆ど残っていないからである。
この人物が,ヴィオールという楽器に改良を加え,その演奏技術を著しく向上させ,その響きは「人間の声」に一気に近づくことになり,この楽器を完成させたと言われる。楽譜を殆ど出版しなかったのは,即興で湧き起こる響こそが音楽であって,書かれたものに価値はないと考えていたからであるという。
この映画のあらすじは次のようなものである。全体はマレの回想によって進められる。
二人の娘を残して妻が亡くなると,サント・コロンブは小屋に閉じこもって楽器の演奏に沈潜し,娘達が成長すると,その技術を教え,彼ら父子の演奏は宮中でも有名になった。これがきっかけで王の楽団への誘いがかかったにも拘らず,「音楽は王のものではない」と拒否し,宮中との関係を断つ。
この頃弟子入りを志願してきたマレに,サント・コロンブは,〈フォリア〉の即興演奏をさせ,それを聴き終えるや否や,教えを授けることを拒む。しかし,共にその演奏を聴いていた娘達の強い要望もあって,マレに自作曲を演奏させる。
そこに,自らとは異なる新たな音楽を認めはしたものの,それでもサント・コロンブは,こう予言する。
「貴方の作る曲は必ずや世に出る。だが,貴方は音楽家にはなれない。」
音楽とは何か?
しばしの期間指導を受けたものの,マレはサント・コロンブの言い付けを破り宮中での演奏をしたことがきっかけで,破門される。しかし,その後も娘と密会してヴィオールの技術を盗み続けるが,宮中での職を得るや献身的であった娘を裏切り,彼女は自殺する。その日からサント・コロンブは楽器を奏することをやめてしまう。
宮中で成功をおさめたマレは,やがて自らの音楽に虚しさを感じるようになる。そして,かつて師が口にした「音楽とは……」という問いに対する答えを知りたくなり,師の籠もる小屋へ毎晩通う。だが,外に漏れるのは師の呟きばかりであった。
そんなある日,突然にその小屋から楽器の音が鳴り響く。「私の話相手は死者ばかりだ。この世の話相手がほしい……」
その呟きを待っていたように,マレは戸を叩く。再会した二人が交わした最初の会話。「最後のレッスンをお願いします。」「いえ,これは貴方への最初のレッスンです。」 そして,「音楽」への問い — 「音楽とは何か?」
マレの答えに対し,師は悉く否定する。「わからない……私にはさっぱり……」と吐露するマレ。しかし,その直後,自信なく答えた言葉に師は激しく反応する。それは驚くべき答えだった。
「死者に対する — 言葉を失った者どもへの — 贈り物」
死と生
もしもこの世が言葉によって造られたとするならば,そして,人間が言葉によって生きるとするならば,言葉を失った者達は「存在」を失った者達でもある。この場合の「死」は,「身体」を失うことというよりも,人間としての死を意味するだろう。
人間は言葉によって生きる。在りし日のその人々の面影を思い浮かべるときに,我々は,その人々の在りし日の声を,同時に聴きはしないだろうか?
「人間の声 les voix humaines」は「生の響き」である。しかし,「人間」を問うこと自体が愚かしく見える現代にあって,「音楽」は「生」であることを已めた。
我々の時代は,ヴィオールの音を掻き消すような雑音に対して,「音楽」と名付けるのである。
旧ウェブ日記2010年3月9日付