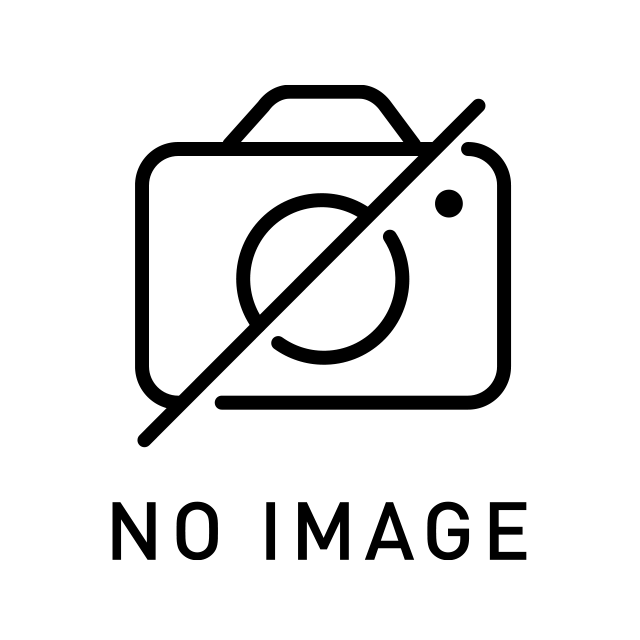先生
私がトラヴェルソ (flauto traverso) と出会ったのは,田中潤一先生の音だった。
それまではずっとリコーダー (Blockflöte) ばかりを吹いていて,バロック音楽を聴いてもフルートには余り心が惹かれなかった。むしろ「出来の悪い楽器」という印象しかもたなかった。その観念を全く変えてしまったのが,田中先生の音だった。
ちょっとしたことがきっかけで,このトラヴェルソを田中先生に習うことができるようになった。私が大学の助手をしていた頃の話である。
おそらく,田中先生のレッスンを受けなければ,音楽の本質的なことを知らずに,私は人生を終えることとなっていたに違いない。
もちろん,それまでも作曲紛いのことはやっていたし,そこら辺の音大生に比べれば楽理などには詳しいし,音楽史の知識や音楽を聴く耳もそこそこはもっていたが,そのときの私は「音楽」に対してかなり狭量でペシミスティックな見方になっていた。
余りにも観念的(idealistic)で,「演奏」された響きそのものは「音楽」ではない,とすら思っていた。しかし,「響き」そのものに対する感性に目を向けさせてくれたのは,田中先生のレッスンであった。
響き
トラヴェルソは,バロック音楽ファンであれば,誰しもが一度は演奏してみたいと思う楽器である。しかし,幼い頃からフルートを習ってきた人でさえ,鳴らすのは容易ではないもので,多くの人は諦めてしまう。仮に,音が出せるようになり,その後続けていったとしても,本当に鳴り響かせることのできる奏者は,殆どいない。
田中先生の指導を受け,その耳ができてしまうと,現在販売されているCDの中で聴くに値するものは殆ど皆無である。逆に,そういう耳をもった人間がいないのではないかとさえ思えるほどである。
レッスンの度毎に注意を受けたのは,発音の仕方である。
普通,レッスンといえば,私くらいの年齢になると「趣味の何タラ」のレヴェルで,好きな曲を復習って,それを心地よく或いは格好良く吹くためのアドヴァイスを受け,うまくできれば褒めてもらうという手合のものになるだろう。しかし,田中先生の最初のレッスンでは,第1オクターブのGのただ一音の出し方を1時間ほど見てくださり,その後,G-A-H と上昇していく練習をしていった。
一音一音でポイントの感覚が異なり,また,音色が異なるということがよくわかった。もちろん,「趣味の何タラ」の様な楽しさなど全くない。しかし,そこには「音楽」そのものがあった。
自分がそれまで考えてきた「音楽」,それは一体何だったのか,と思わされた。
その後,レッスンの回数を重ねる毎に,いろいろな曲をみて頂いたが,詰まるところ,一番最初にやった 第1オクターブの Gの出し方で教わったことが身に付かなければ,何も進歩しないということがわかっただけだった。
トラヴェルソ奏者の中で,このことがわかり本当に表現できる人間は,世界に数名程度だろう。
田中先生にとっても,トラヴェルソの理想は,いつもブリュッヘン(Frans Brüggen)にあった。だから,私にとっての理想は,ブリュッヘンと田中先生の音である。
日本の笛
しかし,田中先生がしばしば引き合いに出していたのは,守安功氏である。二人は二十代の頃にデュオを組み,それまでの日本の古楽奏者にはない試みをしていった。両者とも日本の音楽的アカデミズムには馴染めなかったのであろう。彼らの音楽性は所謂「クラシック」という枠組みでは狭すぎたに違いない。二人とも篠笛を習っていた。田中先生は,この篠笛とリコーダーについて守安さんには一目置いていた。
私は守安さんのことを「リコーダー奏者」だと思っていた。その驚愕すべきテクニックは,「タブラトゥーラ」のCD第1集 (H33u20002) や 「Recorder Duo Yasu」(ALCD-7017) を聴けば明らかである。私が知っている「リコーダー奏者」としての守安さんの足跡は,そこまでであった。そして,いつの間にかアイリッシュ音楽に転向していたようだった。
最初は「リコーダー奏者」の守安さんから「アイリッシュの横笛」の守安さんは想像し難かったのであるが,実際にその音を耳にすると,やはり守安さんの音だと思わされた。現在,音楽史に言うバロック時代のアイルランドに生きたターロック・オキャロラン (Turlough O’Carolan, 1670-1738) の 全曲録音プロジェクト(全7巻) を手掛けておられ,うち第4巻までリリースされている。
アイリッシュ音楽は,実は,日本が西洋音楽を取り入れる上で,大きな役割を果たしている。日本人の叙情性を擽るメロディーの殆どは,アイリッシュ音楽のパクリではないかとさえ思われる。勿論,アイルランド固有の音楽語法(和声・リズム法)があり,また様式があるから,余り単純化もできない。しかし,日本人には分かり易い音楽だと思える。
そうは言っても,「分かり易さ」というのは,ときとして,「都合よく受け入れられる」ということを意味する。そのとき人は漫然とそれを聞いている。
守安さんの横笛の音は,「音楽」のある境地に達している。この音も,やはり私にとっては,理想なのである。アイリッシュ・フルートとフラウト・トラヴェルソとでは,楽器として異なる。それでも,笛(flute)であることによって,発音原理は共通する。そこには通底するものがある。
守安さんの音には,「笛」としての「理想」がある。守安さんに失礼ではあることを承知の上で敢えて言わせて頂けば,「この音が,あるいはバッハの,あるいはヘンデルの,あるいはエマヌエルの曲として響くならば,さぞかし驚異的な音楽となっただろうに」と,私には思われる。そういった意味での「理想」である。
言い方を換えれば,私は,ブリュッヘンにはバロック固有の音楽語法という点で共感できるとするならば,田中先生と守安さんには日本人の笛の感性として共感できるのだろう。そして私はブリュッヘンの出す音にさえ,日本の笛の音を聴いているのだろう。
勢いついでに言えば,日本人ほど,笛(flute)の奏法を洗練させた民族は存在しない。私はその感性を信じたい。そして,所謂「クラシック」の西洋気触れした奏法に毒され,この感性を捨て去ってしまったフルーティストほど有害なものはないと思う。実のところ,そのような輩ばかりであるが。
ハンブルク・ソナタ
おそらくトラヴェルソを吹く者が,フルート・ソナタの最難関作品として挙げるのは,C.P.E.バッハ (Carl Philipp Emanuel Bach, 1714-1788) の通称〈ハンブルク・ソナタ〉と呼ばれるト長調のソナタ (Wq133/H564) であろう。これはキーが一つだけ付いたフルート (one-key flute) で演奏できる限界だと思われる。
例えばこの曲を例にとった場合,Barthold Kuijken版 (ACC 24171) と有田正広版 (COCQ-85204) とでは,圧倒的に後者の方が演奏技術は上である。クイケンは「天才」と言われるほどに,難なく音を出してしまうが,まるで「親爺の鼻歌」にしか聴こえない。これに対して,有田氏の作品分析と構成,そして表現技術は完璧といっていいほどである。これはいわば「手本」である。
しかし,それでも私には「音楽」に聴こえないのである。「美しい標本」を見ている様には思えるが,「作品の生命」を感じることができない。
よもや 音楽史における Sturm und Drang の中心的人物であり,自らも演奏中に陶酔の余り涙を流しながら奏したと言われるエマヌエルの手になる作品である。勿論,モダン(クロマティック・フルート)の演奏では,この作品の理想を決して表現できないし,実際,殆ど全ては失敗に終わっている1。
そんな訳で,私にとって,この〈ハンブルク・ソナタ〉における最高の理想は,田中先生の演奏である。これまで演奏会で3度ほど聴いているが,精度では有田氏の演奏が勝っているものの,「作品の生命」を感じるのは,やはり田中先生の演奏である。
私にとって「音楽」は「生命の息吹」を表すものだからである。
旧ウェブ日記2010年2月1日付