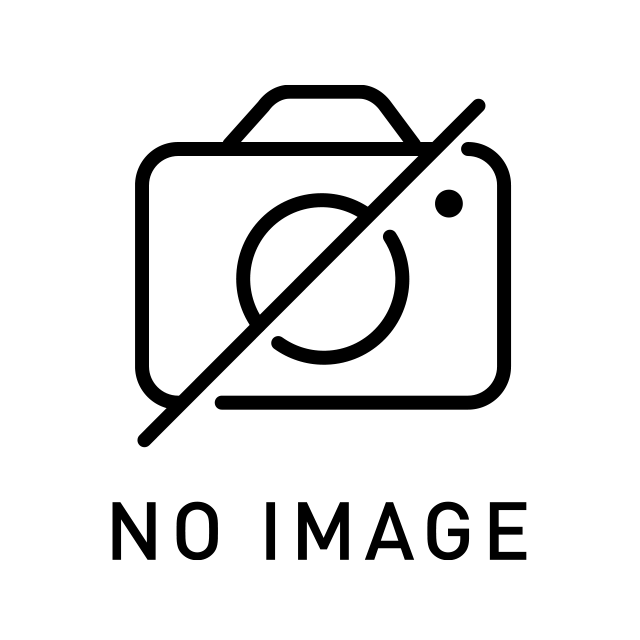音階論(
今日は一つだけいいことがあった。それは アリストクセノスとプトレマイオスの「ハルモニア論」の訳本が届いていたこと。山本建郎氏の訳だ。
古代ギリシア音楽論について語ろうとすれば,この2つの「音階論」に言及せざるをえなくなる。しかし,これまでこれら2冊の完訳というのは無かったのではないだろうか。
山本氏は,アリストクセノスの音楽論に関する学位請求論文を筑波大学に提出し,私が博士学位をとったのと同じ年である1999年に,博士学位を取得しておられる。
実は,私もその公開審査を見学しにいった。そのときのことは余りよく覚えていないが,ただ審査員が「音楽論は哲学ではない」というような余りにも幼稚かつ無知な批判をしていたのを耳にして,密かに憤った覚えがある。
その愚かな批判に耐えながらこうして氏の研究成果が公開されることになったことを心から祝福したい。
偉業
私は氏と直接面識はないし,これまでやりとりしたこともない。
しかし,この「ハルモニア」研究における重要な文献を多くの研究者に知らしめるという偉業は,当然,近代における「ハルモニア」の問題に取り組んでいる私の様な研究者にとっても,勇気付けられるものであるし,伝承の過程において何がどのように取り違えられてきたのかという問題についても,精確に理解することの手助けとなる。
また「ピュタゴラス音階」なるものが全くの理念的なものであり,実際には使用されたことはないということの傍証にも役立つものとなる。ヨーロッパの数的秩序論を支えつづけた自由4学芸の「音楽」における理念を「ピュタゴラス音階」なるものが象徴していたとするならば,自由4学芸そのものが理念として留まり続けたという可能性を,強く示唆することになるかもしれないからだ。
これはまた「数学」を扱う「数学史」と「存在論的数論」を扱う「数理思想史」の区別の問題にも関わる。私がやらねばならないのは,メルセンヌにおける「数理思想」において,この区別を例示することである。
私が大学院に入ったときに初めて文献らしい文献を購入した最初の著作がM・ウェーバーの『音楽社会学』であったが,それを手にしたときと同じ興奮を,今おぼえている。
旧ウェブ日記2008年5月22日付