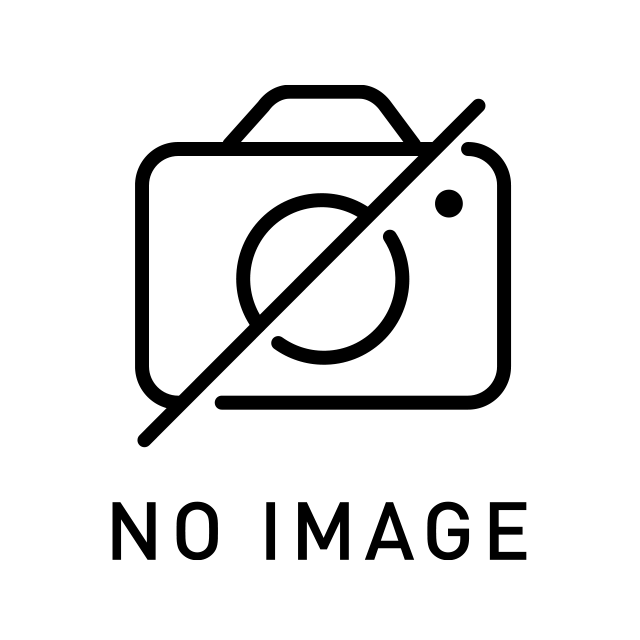忘れもしない2009年4月のことだった。哲学の授業を終えて研究室で休んでいたとき,一人の新入生が飛び込んできた。
その頃私は,古代から近代までの音楽思想の流れを追い,デカルトとメルセンヌとの間で交わされた音楽理論に関する宇宙論的な問題が如何なるものであったのかを説明するという実験的な授業を行っていた。その学生というのは芸術学科に入学し,自分でもピアノと声楽の演奏をし作曲もするということで,たまたま私の授業に出て感じるものがあり,音楽思想に関心をもったらしい。
そのとき,自作CDを渡され,何やら他愛もない音楽話をしたが,まず私自身はポピュラー音楽には全く興味はなかったし,ましてやモダンピアノなどというのは,それこそ音楽を世俗化へと導いた道具に過ぎないと思っていたので,余り耳にする気にもならなかった1。
何よりも,その頃には大学や研究活動の様々な事柄に倦み疲れ,あらゆる不毛な人間関係を断ち切り,また,自らの人生の一部でさえあった音楽そのものとも完全に決別しようと,所持していた楽譜,音楽書,CDの類の一切を捨てようと思い始めていた。そんな他人の内面を全く気にもせず,ピアノや音楽の話をしたがる高校生あがりの若者の熱気が,些か鬱陶しく感じられた。
しかし,彼が渡してくれた名刺らしきものに記されていたBLOGサイトにアクセスし,彼の日々の内情を知るにつけ,子どもから大人になっていく不安定な時期の心の揺らぎや,将来音楽活動で生計を立てていきたいという焦りなどを知り,私も自らの音楽人生に節目を付けるために,彼の人生にほんの少しだけ関わり見届けてみようと思うようになった2。
真夏のある日,彼は「新曲ができました,即興で作ったんです。」と言って,音源を渡してくれた。家に帰って,何の期待もなくそれを流してみた。感想の一つも言わねばならないだろうからと,早回しで適当に聞き流してみるつもりだったのだが,思わず聞き入ってしまった。
そういえば,少し前に,私が「何もしたくなくなり何も考えたくなくなるときには,散歩に出て,江ノ島の中をひたすら歩く。」というようなことを話したことがある。そのとき彼は「江ノ島には最近ほとんど行かなくなりました。」というようなことを言っていたのだが,その少し後に行って,帰宅してからこの曲を演奏したということだった。
曲名は《褪せた七色のスケッチ》。
彼はこれを「即興曲」と言っていたので,「即興曲という楽曲形式は,即興した曲という意味ではなくて,あたかもその場で即興されたかのように自由な形式のことを指すんだよ。」と教えてあげた。ただ,彼はこれを電子ピアノの録音スイッチを押すと同時に,本当に即興で自らの胸の内を音言語化して纏め上げた。
これも,彼が,人が言葉を語るのと同じぐらいの自然さで音楽を奏でることができる能力と技術とをもっていたからこそ可能となったことである。二十歳になったばかりの彼が,その時の自らの内面をそのまま吐露し,その場で音として形作った儚く脆い純粋な結晶だったのだ。
たまたまネットにその作品がアップされていたものを見つけたので,さっそくコード埋め込みをしてみた。(勿論,ネットに音源をアップするときにはある程度音質を落とさなければならなくなるので,こうしてネット公開された作品の場合,どうしても音に多少の歪みが出てくることは致し方がないであろう。)
最初は物憂げな装いで始まり,しばらくして僅かの希望を感じる曲調へと変化していくものの,幾度となくかつての改悛へと引き戻される(1’40″〜)。しばらくこの希望と不安との交錯した状況は続くが,それでも希望を見出そうとするかのような曲調に転じて曲を終える(4’18″〜)。
これは以前に渡された彼の如何なる音源とも,全く違う響きだった。再生する直前,あれほど気乗りがしなかった自らを恥じた。そればかりか,聞き終えてしばらく涙が止まらなかった。ただ「救われた」と思った。
何か私の脳裏には,天空と陸地との間に広がる薄明の中で,翼ある者が天に向かって飛び立とうとしながらも逡巡するような光景が過った。そして,こうした魂の彷徨は,誰しもが若い頃に経験するだろうし,その想いが純粋であればあるほど,その「痛み」は胸の奥深くに刻まれる。
その「痛み」こそ,魂の純粋性の証なのだろう。そればかりか,人は,そのときの純粋性には二度と近づくことはできない。純粋性において,そのときの自分を決して超えることはできない。
大人になるということは,世俗化し社会に迎合し汚れるということ以外の何ものでもない。あれほどの「憧れ」をもって歩んだ道を進み続け到達したときには,その「憧れ」を失い,傲慢の罪を負う汚れたものと成り果てる。
その数日後,彼と会ったときに,私はこう言った — 「将来,君が仮にどのように成功することとなったにせよ,今このときの自分に憧れる日が来るだろう。」
今,彼がどこで何をしているのかはわからない。また,それを知るつもりもない。ただ,私にとって今も重要であり続けるのは,この音楽が「在る」という事実である。
何もしようとはせず、ただただ流れ、それでありながら人の心を打つ音楽 — それは、この世で最も恐ろしい音楽だ。それは人を恋をした状態に — 魂が美に略奪され抜け殻のようになった状態に — 陥れるからである。
注
- 実は私も,正規の教育こそ受けてはいないのだが,父の早くに亡くなった母親が貴族院の出で,父はドイツ人教師にピアノの基礎を徹底して叩き込まれ,私も小中学生の頃に半強制的にその父にピアノの基礎を叩き込まれた。その後は独学で訓練をして,高校〜大学の頃にはバッハの《Inventionen und Sinfonien, BWV 772-801》や《Das Wohltemperirte Clavier, BWV 846〜869》を好んで弾いていた。しかし,自分には鍵盤楽器の才能はないと見切りを付け,自ら進んで鍵盤そのものに触ることもなくなった。私にとってピアノは,謂わば「遠い昔に喧嘩別れした恋人」のような存在である。
- 彼には「弟子にしてほしい」とまで言われたのだが,音楽人生を閉じようと思っていたそのときの私は「今更……」としか思えなかった。彼もしばらくは私のアドバイスなどを受け入れていたのだが,その後,様々な行き違いがあり,この不安定な師弟擬きの関係は半年ほどで終わりを迎えるに至った。私もこのことがきっかけで,二度と学生とは教室内でしか関わるまいと決意するに至った。